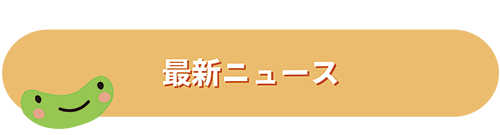- 2025/03/11
- バックナンバー
- 最新ニュース
BPSDケアプログラムの実践
東京都と東京都医学総合研究所が開発した「日本版BPSDケアプログラム」は、認知症の人の行動・心理症状を軽減する。科学的に効果のあるプログラムとして証明されており、国際的にも注目されているという。昨年度からは認知症チームケア推進加算Ⅰの算定要件の一つにもなっている。本プログラムを実際に活用している認知症ケアの実践現場を取材した。
「考える癖」をつける方法として活用
「すべては『利用者さんへのケアを良いものにする』、そこにつながっています」
まっすぐこう言い切るのは、特別養護老人ホーム鳳仙寮(社会福祉法人府中西和会、東京都府中市)の不動田敏幸施設長だ。不動田さんは東京都の認知症介護実践者研修や実践リーダー研修の講師も務める。「従来型特養だけれどもグループホームのようなケア」を目指しているという。
鳳仙寮がケアプログラムを導入したのは昨年夏。そのころ、不動田さんは、立ち上がり頻回な認知症の入所者に対して、職員が「おやつがあるよ」と注意をひく場面を見かけた。一時的には座るかもしれないが、根本的な解決にはならない対応だ。その人が繰り返し立ち上がることの意味を「考える癖」や、経験と勘ではないケアの方法、コミュニケーション力を身につけてもらうためにケアプログラムが活用できると考えた。
不動田施設長(前列左から2人目)と法人職員の皆さん
これまでに、転倒リスクの高い人や、手はかからないが無気力な状態が続いている人など4人の入所者にプログラムを実施した。
入所者に関わる介護職や看護師など4~5人でチームを形成。23項目のニーズリストを使って状態を評価し、それぞれの情報を話し合いながら1枚にまとめていく。その情報をアドミニストレーターの不動田さんがDEMBASEというシステムに入力。優先度の高い困りごとからプランを実行していく。分析・評価したことと、提供するケアがきちんとリンクしているかも確認する。
例えば、85歳の女性の例。頻回の立ち上がりに加え、テーブルに置かれた食器などを手繰り寄せたり、目の前の人に暴言を吐いたりしていた。元々社交的だったという情報を踏まえて、利用者同士や職員との関係を作るため「他の入居者と一緒に朝10時に花壇の花に水やりに行く」というプランを立案。職員が間に入って他の入所者との接点をつくるとコミュニケーションが生まれ、立ち上がりは減少し、表情も柔和になった。「問題行動」は、他の人に話しかけたいという意思の表れだったようだ。
「その人の行動の背景が分かると、ポジティブに利用者を見られるようになります。すると、利用者も何かを伝えようとするようになる。数値が下がることよりも、職員の視点や行動が変わったり、“なぜだろう”と考える機会が増えるのが最大の効果ですね」(不動田さん)
そして鳳仙寮では、職員に、利用者の行動の意味を考え理解する習慣が身に着いたと判断した段階で、プログラムを終了する運用をしている。
「介護報酬改定で認知症チームケア推進加算がなぜ新設されたかと言えば、認知症ケアの現場で適切なケアができていない現状があるからだと思います。その人に良いケアを提供することが目的なので、私たちの施設では全員に長い期間算定しなくてもいいと考えています。利用者さんや家族の負担も少しでも少ない方がいいですから」(不動田さん)
施設に入所する高齢者のほとんどは仕方なく入所している。本当は家に帰りたい。それがニーズだ。
「どうしたら“ここならまあいいや”と折り合いをつけてもらえるか。職員がしっかり関わりを持つことでようやくそこにたどり着けて、BPSDが抑えられたり、症状が出ても対応できたりするようになるのではないでしょうか」
利用者のニーズが満たされるためのケアとは何か。どう実践するか。鳳仙寮は、そのために認知症ケアプログラムを活用している。