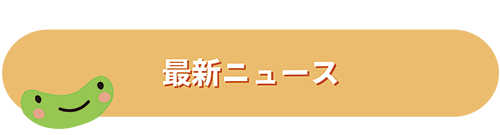- 2025/03/25
- バックナンバー
- 最新ニュース
日本福祉大学福祉社会開発研究所と日本福祉大学ケアマネジメント技術研究会は2月23日、20回目となる日本福祉大学ケアマネジメント研究セミナーを開催した。ケアマネジャーが身に着けるべき実践技術をテーマに、現場で行われているケアマネジャーの育成事例を紹介したほか、実践者も交えて議論した。

「ケアマネジメントの本質と求められる実践技術」と題して基調講演をした、北星学園大学社会福祉学科の畑亮輔准教授は、ケアマネジメントの本質は、①利用者の「生活ニーズ」に着目した支援、②利用者と専門職の協働で導き出したリアルニーズを充たす支援、③様々な社会資源(制度・分野横断)の活用・調整――にあると説明。この本質を実践する上では、縦割りで利用者のサービス受給によってのみ報酬が発生する制度設計、法定研修での演習・実習教育の不足や、ひとり業務によるOJTの不足等の養成・育成面での課題があると述べた。
一般的な専門職の養成プロセスは、教育→現場実践の順だが、ケアマネジャーはその逆で、他の職務や資格での実務経験→教育・現場実践と、実践しながら教育を受ける。にもかかわらず、ケアマネには肝心のOJT体制があまりないと指摘。実践技術習得には、学習と実践を繰り返すことが必要で、法定研修では、講義を聞くだけでなく、ロールプレイとシミュレーションの適切な組み合わせが必要と説明。指導する立場にあるケアマネジャーとの同行訪問やスーパーバイズが不可欠だと述べた。
地域で初任者と主任ケアマネジャーそれぞれのモニタリングと担当者会議に同行するなど実習形式で行われる地域同行型研修は、平成26年度老人保健健康増進等事業の調査研究から開始。発表された5地域では、すべて行政が研修を予算化し、ケアマネジャーの費用負担はないという。日本ケアマネジメント学会の白木裕子副理事長は、ケアマネジャーを育成しようとする都道府県の意欲の表れだと評価した。
研修と実践の連動性見える仕組み構築を
「ケアマネジメントの人材育成に求められる『実践技術』とはなにか?」をテーマとしたシンポジウムでは、ケアタウン総合研究所の高室しげゆき氏がコーディネーターを務め、実践者や参加者を交えてディスカッションを行った。「学ぶべき項目をどう伝え(手法)、どのように学ぶ機会をつくるか」との高室氏の問い掛けに対し、北海道北見地域介護支援専門員連絡協議会の笹谷里美副代表は「適切なケアマネジメント手法等を活用した抜け漏れのない情報収集も大切だが、その前段階でバイスティックの7原則の知識等を活用し、本人の強みを引き出し、言語化し、サービススタッフの方々に伝えていく力を養うことが大切」と述べ、基本的な相談援助知識・技術の習得が必要と訴えた。
また、コメンテーターの畑准教授は、本質的な支援には、「業務をするため」のスキルではなく、「専門職」としてのスキルが大切であるのに、ケアマネジャーは多忙ゆえに「業務」のためのスキル習得に意識が向きやすくなっているのではないかと指摘。秋田県の介護支援専門員協会の調査を引用し、「アセスメントが苦手と答える人が多い一方で、ケアプラン原案の作成を苦手と答えた人は少なく、アセスメントとケアプランの作成が切り離されて考えられているのではないか」として、専門職の価値・倫理教育を徹底した上で、研修の学びと実践技術が連動した仕組みをつくる必要があると強調した。