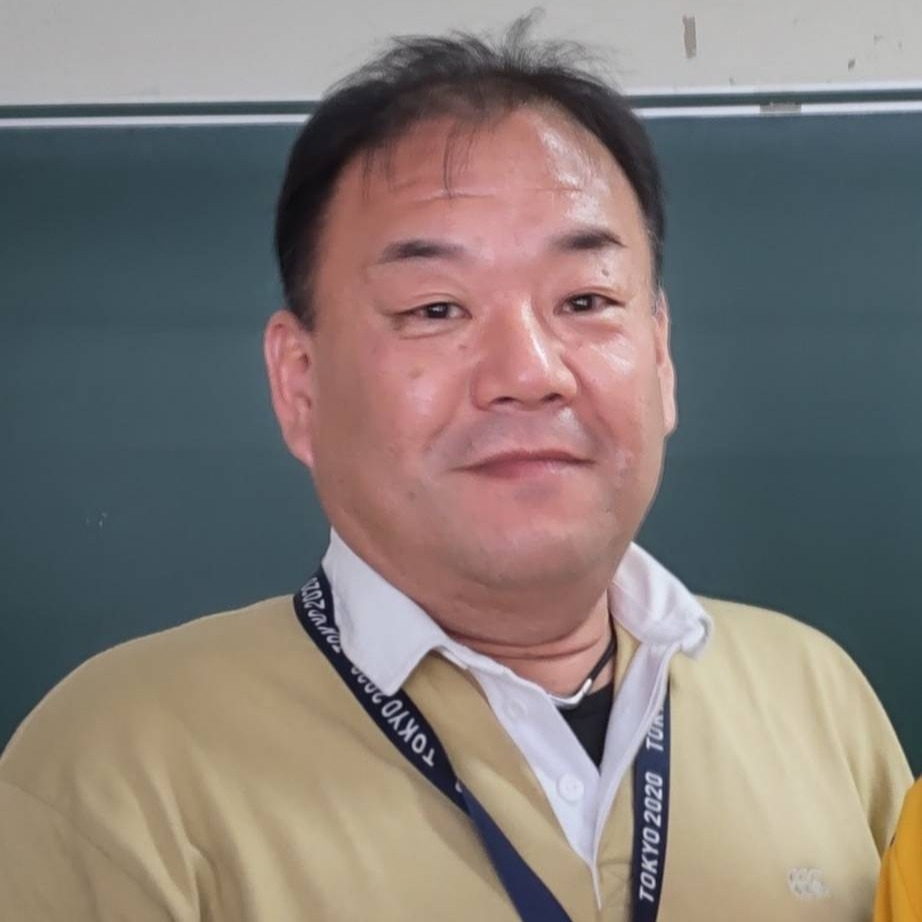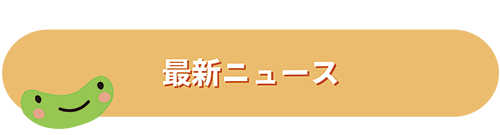- 2025/04/15
- バックナンバー
- 最新ニュース
責任主体を明確に再構築を
期待していた介護予防支援の指定事業所が増えず、地域包括支援センターの業務多忙も緩和されない。この事態を招いた要因を紐解くには、介護予防の導入当時からの経緯を知ることが必要だろう。ということで、介護保険創設からケアマネジャーとして制度見直しの荒波と闘い続けている大山弘一郎さん(昭島市東部地域包括支援センター・センター長)と日下部浩二さん(あきる野市、草花ケアサポート・管理者)のお2人と振り返ってみた。(編集部)
編集部
介護予防が導入されたのは2006年。今振り返っても最も現場にインパクトを与えた制度改正だった。
大山さん
私は現在、昭島市の地域包括支援センターの管理者ですが、当時は居宅介護支援事業所や訪問介護など在宅サービス事業を経営していました。介護保険制度では当初から、要支援者には予防給付のサービスが提供されていましたが、要支援者が増え続けるなかでその効果が上がっていないということが問題視されたわけです。要介護と同じサービスメニューでいいのかとか、市町村事業で予防目的で行われている地域支え合い事業や老人保健事業との継続性や一貫性がないなど、あれこれ反省点があると。だから予防給付の内容、ケアマネジメントシステムを刷新すべきとして、要支援1・2というカテゴリーをつくり、予防プランは新たに市町村が運営する地域包括支援センターに移行した、という経緯でした。
この見直しが出たとき、私だけでなくケアマネジャーの多くは憤りを感じました。ケアマネジャーに任せておいたらどんどん重度化してしまう、だから予防はケアマネジャーの仕事から外したほうがいい、と言われたわけですから。
ところが、地域包括の保健師が中心となってプランの担い手になるという構想は上手く機能しなかった。その理由の一つは、地域包括を直営だけで運営する市町村が少なかったためです。結局、委託という形で再度ケアマネジャーにお願いすることになった。でも市町村直営の地域包括で担ってもらうことを前提に、非常に安い金額になったのですから、進んで委託を受けるメリットもなくなってしまいました。
日下部さん
私も2000年からケアマネジャーをしていて、要支援から要介護までかかわり続けられることがケアマネジメントの魅力だと感じていました。それが半ば強制的に大事な利用者さんを取り上げられ、全く納得がいかなかった。
要支援の人たちにとってもケアマネジャーを選ぶことができなくなるのは措置制度に逆戻りするのと同じで、介護保険の理念に反すると思いました。なので、うちの居宅介護支援事業所では一切、地域包括からの予防プランの委託は受けない方針でやってきました。
それが20年経って、地域包括がパンクしそうだから居宅介護支援事業所に指定を取ってほしいと言われても、改正の意味は何だったのかと。予防には予防のケアマジメントがあるというなら、やはり委託するべきではないと今も思います。適当に都合よく制度を変えているようにしか見えません。
大山
予防サービスの報酬設定にも問題がありました。要支援1や2の人は自立する可能性が高い人たちなのに報酬から逆算して要支援1なら週1回と画一的な対応が一般的になってしまいました。事業者と利用者で利用回数を決めるようになっているにもかかわらず、です。制度の問題だけでなく、現場も自立のための予防サービスをどう提供するかということに真剣に向き合ってこなかったことも事実だと思います。
編集部
市町村も責任主体という意識が薄いのでは。指定事業所が増えていなくても地域包括がなんとかしてくれている、みたいな感じです。
日下部
市町村に対して一番言いたいのは、利用者、市民への説明責任を果たしていないのではないか、ということです。介護保険が始まってもう25年経つのに、いまだにケアマネジャーから初めて説明を受けるという人が多い。
本来は介護保険も医療保険と同じように、必要になったらサービスを利用して、必要じゃなくなったらやめるもの。国や行政が当初から国民に説明していれば、そもそもあんな強引な介護予防を作らなくても済んだのではないかと思います。
それに予防プランは地域包括も居宅も受けられるけれど、要介護の人のプランは居宅しか受けられません。ケアマネジャー不足で、要介護者の難民問題が深刻になっています。
大山
昭島市は地域包括が5カ所ありますが、どこも予防を引き受けてくれる居宅介護支援事業所を探すために、1日何件も何件も電話をかけている状態です。居宅も疲れ果てている。相談にきた人に、自力でケアマネを探してくださいと言っても探すことができなければ、餓死してしまう人が出てくるかもしれない。
行政に何とかしてほしいと何度もかけあって、ようやく市内の全居宅介護事業所の受け入れ状況を市が一括して把握し、開示するようになりました。一歩前進だと思いますが、やはりどこのケアマネ事業所も常に受け入れる余裕がほとんどない状況であることも改めて浮き彫りになりました。この現状の深刻さを行政が共有したことで、もっと現場と利用者への支援に動き出してもらいたいと思っているところです。要支援であろうと要介護であろうと、何かしら理由があって介護保険を必要としている人がいる。そこに国も行政も責任を持って向き合うべきです。
編集部
ケアマネに協力してもらいたいなら、せめて報酬は大幅な引き上げが必要ですね。
日下部
もちろんです。先ほども言ったように、ケアマネは基本的に自立に近いところから要介護になるまで、長くかかわるほうがその人の生き方を深く知ることができると思っている人が多い。ただ、報酬だけでは場当たり的で、やはり介護予防が今の仕組みになってどれほどの成果が出たのか、20年の検証をきちんとすべきです。
大山
ケアマネの業務負担軽減についても、もっと現場に裁量権を与えて効率化できることは山ほどあります。医療保険の話が出ましたが、介護保険も診療所方式というか、ケアマネが訪問するのではなく利用者に来てもらってケアプランを発行するというような仕組みにすればいいと思っている。そこでしっかり話を聞いてあげれば、利用者がケアマネを選ぶ意識も高まるでしょうし、コミュニティづくりにもなる。件数も増やせるでしょう。予防だけにとらわれず、制度を再構築するくらいの気持ちで検証してもらいたいと思います。