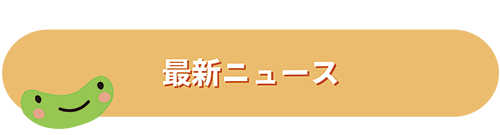- 2025/05/07
- バックナンバー
- 最新ニュース
日本在宅介護協会(千代田区、森山典明会長)は4月18日、都内でセミナー「ぶっこわそう! BPSDの捉え方」を開催した。訪問介護事業などを手掛ける大起エンゼルヘルプ(荒川区、小林由憲代表)の介護事業部部長・和田行男さんと介護老人保健施設愛生苑(広島県庄原市)の管理医師・戸谷修二さんが登壇。認知症状態の人の言動を安易に「BPSD」という言葉に当てはめず、その言動の背景を探り、対応策を考えることが重要だという意見などが交わされた。
かつて「認知症」は「痴呆症」と呼ばれていた。認知症状態の人の尊厳を欠くような蔑視的名称だという指摘が多く寄せられたことから、2004年に厚生労働省が痴呆症に代わって認知症という名称を提唱。「同様にBPSDも問題行動という名称から変化したが、認知症状態の人の価値を傷付けるような考え方をしている医療・介護従事者はまだ多い」と和田さんは問題提起した。
戸谷さんは認知症の周辺症状について「心が示す自然な反応」であるとし、「症状という呼び方は不適切だ」と訴えた。周辺症状の仕組みについては「脳機能の変化は作用しておらず、環境や身体状況などの多様な要因によって表れる心理的な反応」だと解説。
和田さんは介護施設で勤務していた頃、施設の廊下を徘徊していた入居者への対応として、施設内の居室の鍵をまとめた束を渡したという。「その方は若い頃に用務員の仕事をしていたそうです。廊下を周回して部屋の戸締りをする習慣が残っていたのでしょう」。その後、入居者は居室の戸締りを確認しながら廊下を歩くようになり、「施設内では用務員のような存在として受け入れられていた」と話した。
戸谷さんは、「高齢者が暮らしていた環境や生活習慣などから、BPSDが表れる具体的な理由を探ることが適切なケアに繋がる」と呼びかけた。
新人介護職員や学生らが熱心に聴講した