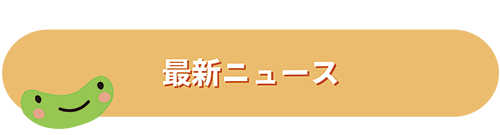- 2025/07/08
- バックナンバー
- 最新ニュース
医療・介護連携で老年学会と合同シンポ
日本ケアマネジメント学会は6月28日から2日間、日本老年医学会などと7学会合同の学会を千葉市で開催した。ケアマネ学会は約1千人が参加した。28日には合同のシンポジウム「医療と介護の専門性、どうつかむ・どう実践する・どうつなぐ」を開催(写真)。患者・利用者を支援するために、医療分野と介護分野の専門職がどう連携するかについて、医師、看護職、ソーシャルワーカー、ケアマネジャーが各現場での実践を報告しながら、職種や制度を超えた連携の在り方について議論した。
一般社団法人ネイバーフッドケアの吉江悟代表理事は、千葉県柏市で訪問看護ステーションと、第2層の生活支援コーディネーター、住民主体の通いの場が一体となった拠点を運営している。吉江代表は、「本人の意思をどうつむいでいくかについては、多職種が参加するさまざまな担当者会議で学んでいくことが重要」と指摘。近く移転する新たな拠点では、多く団体や人に出入りしてもらい、地域看護の機能を発揮する方向を目指すと語った。
12人のソーシャルワーカー(SW)が所属するというJA愛知厚生連江南厚生病院患者支援室の野田智子室長は、入退院支援時に認知症患者や家族に頼れない患者が増えており、「本人の意思表明をしておくことが重要になる場面が増えた」と現場の実感を報告した。 それに伴い行政や地域包括、ケアマネ、成年後見人などさまざまな支援機関との連携も増えているという。そこで、同院をはじめ地域の複数の医療機関で、▽入退院支援や患者に関する相談などを一元的に受け付ける窓口を外部に公開▽地域のケアマネとのやりとりを行うための共通様式の整備▽地域との定期的な協議の場――などの共通ルールを検討しており、今年度末にルールをまとめたガイドブックを作成予定と紹介した。
杉並区のケアマネ事業所の管理者で、東京都介護支援専門員研究協議会理事長を務める相田里香氏は、市区町村による包括的支援体制整備を目指す中で、保健医療福祉介護のざまざまな場にケアマネも参画するようになっていると話す。その際、ケアマネが利用者の意思決定支援を担うために必要なこととして、▽多職種の中で視野を広げる▽地域の実情に応じた協働化▽DX▽1人で何でもできるより仲間との信頼関係――などを挙げた。
討論では、相田氏が紹介した利用者の事例を基に、各専門職が患者・利用者にどのようなスタンスで関わるべきかが話し合われた。ALSと診断された女性が、医療者や支援者が必要なサービスにつなごうと急ぐ様子に対し「私を追い越していかないで」と訴えたケースだ。
看護師の吉江氏は、「医療職と福祉職を比べると、医療職の方が追い越しがちという感覚があったが、実際には職種によらず追い越しがちな人もいる。全く追い越さないのも問題」とバランスの難しさを指摘。
パーキンソン病やALSなどの神経内科疾患や、脳血管障害後遺症などに特化した在宅医療専門クリニック(文京区)の石垣泰則院長は、患者に対し医師単独ではなく多職種協働で対応することが診療のポイントとしつつ、「医師の仕事の役割として、先に走らないといけないところがある。ただ、病院で診断を受けたときに医師から受けた説明のほとんどが記憶に残っていないという患者の話も聞いた」と述べ、ケアマネのように伴走する存在が重要との考えを示した。
相田氏は、「患者や家族との距離を保ちつつ、信頼関係をつくるには、相手の話を受け止めるだけでなく、相手がしてほしいと思っていることにどう近づけるか。そのコミュニケーション術を磨いていかなくてはいけない」と改めてケアマネの役割を強調した。