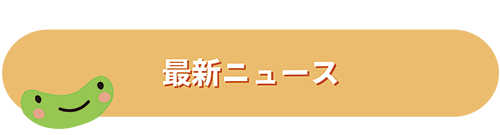- 2025/07/22
- バックナンバー
- 最新ニュース
鉄道弘済会(森本雄司会長)は5日から2日間、今年度の社会福祉セミナーを開催した。テーマは「社会福祉の『支援』はどこに向かうか」。社会福祉士や介護関係者のほか、学生、医療関係者など700人超の申し込みがあった。3人の実践者が若者支援の活動を中心に紹介したが、対象分野にかかわらず求められる「支援の根っこ」が見えたシンポジウムだった。
「新たな支援のかたち」を探る講座では、コーディネーターを務めた立教大学コミュニティ福祉学部の川村岳人准教授が企画の背景を説明。社会福祉はこれまで申請主義の原則に基づいて運用されてきたが、対象者の中にはそもそも介護保険制度を知らない人や、生活保護制度の受給にはスティグマを感じている人が少なくない。その中で生まれつつある「新たな支援」について3人の実践者の報告を受けた。
障害者支援施設や乳児院を運営する社会福祉法人北翔会の大場信一理事長は、措置時代のソーシャルワーカーとしての仕事を振り返った。家族の意向を踏まえて知的障害者施設に入所させた児童から、入所後に“私はあなたに施設に入れられた”と言われがく然。家庭で対応できなくなれば施設入所するのが一般的な支援だった時代に「良い支援をしていたと思っていた」。「当事者の思いを実現するような支援がこれからの支援ではないか」と述べた。
長野県上田市にある劇場で駆け込み宿を運営しているNPO法人場作りネット理事の秋山紅葉理事は、電話やSNSで困り事を抱える人の相談対応や、誰でも1千円で泊まれる「やどかりハウス」の入居者たちと仕事や創作活動を通じ、支援する・される関係に固定しない関係性を基盤にした文化の創造を実践していると紹介。「私たちは困りごとを訴える声を頼りに、その下にある社会問題を誰でも目にしたり触れたりできるようにして、価値観や信念を変え、生きていて良いと考えられる社会を作りたい」と訴えた。
荒井佑介氏は、親を頼れない若者を支援するNPO法人サンカクシャの代表理事。サンカクキチという居場所を東京・池袋で週4日開所。住まい確保のためのシェアハウスも7部屋運用。月額家賃3万5千円。生活に困窮した若者からの相談が多く、部屋は常に満室だ。中には自殺願望が強い若者もいる。まず居場所を確保し、スポーツやドライブ、バンジージャンプなどを一緒に楽しむ中で、本人の意欲や自信が回復していくと報告した。
支援者の役割についても議論した。秋山さんは、当初は個別に相談支援をしていたが、どこまで支援すべきかに悩み一旦活動を停止。「私たちが全部引き受けるのではなく、一緒にやり、助かり合う」という方針を決めて、活動を再開し現在に至ると話した。
荒井さんは、人材養成について課題を提起。「支援活動は鎧を脱ぐことが必要だが、知識を付けることで鎧を身に着けることになりがち」なため、現在は研修ではなく、スタッフ同士の対話や勉強会で学ぶ機会を確保しているという。
川村准教授は、「3者に共通するのは、ともに悩むということ。問題に直面した際に、ともにいるしかできないという支援者としては居心地の悪い状況にとどまる覚悟を持つことが、新しい支援の中核にあるのではないか」とまとめた。

申請主義を超える福祉について議論