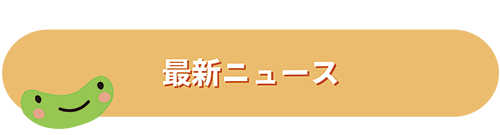- 2025/07/25
- バックナンバー
- ピックアップ記事【1面】
2012年に創設された利用者の居宅を定期的に訪問するサービス「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」。地域包括ケアシステムの中核を担うサービスとして制度に位置付けられてから今年で13年。他の介護保険サービスと比べると、浸透しているとは言い難いのが現状だ。また、27年度の介護報酬改定では、夜間対応型訪問介護との統合の検討も予定されている。定期巡回の普及の課題とその未来について、考えていきたい。
定期巡回は、中重度になっても地域で住み慣れた暮らしを続けられることなどを目的として、2012年に創設された地域密着型サービスだ。一日に短時間・複数回の訪問を行い、緊急時には介護や看護スタッフがかけつけられる体制を整えている。地域包括ケアシステムの構築に向け、その中核を担うサービスとして期待を寄せられていたが、22年4月時点で定期巡回の請求事業所数は1151事業所(図)と、開設当初から13年経つ今も普及は進んでいない。さらに、24年度の介護報酬改定では、訪問介護と並んで基本報酬が減額。受け取り方によっては、定期巡回の設立当初に集まった期待から方針転換し、サービスの縮小を示唆する動きとも捉えられかねない。
しかし、厚生労働省認知症施策・地域介護推進課の吉田慎課長は「高齢者が要介護状態となった場合であっても、可能な限り在宅で暮らし続けることができるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護をはじめとする訪問系サービスのニーズに的確に対応していくことが重要」と位置付け、今後もその重要性は変わらないと強調する。
同省が22年度に行った調査では、介護人材不足のほか利用者・家族の認知度不足が普及を阻む要因として浮かび上がったという。また、夜間の人手不足やケアマネジャーの認知不足も課題だ。(以下略)