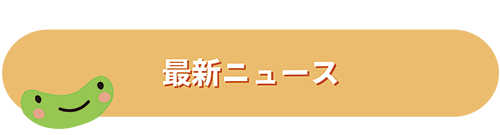- 2025/07/29
- バックナンバー
- 最新ニュース
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下、定期巡回)をはじめ、夜間対応型訪問介護、訪問介護、障害福祉サービスの居宅介護などの事業所を運営する「いるてと」(東京都三鷹市)。今年で設立3年目の介護事業者だ。提供者側が利用者の生活に合わせるサービス提供で、要介護者ののびのびとした在宅生活をサポート。介護職の研修講師もしている前川武嗣代表と、役員で障害者支援に長く関わっている東郷天音さんの2人のほか、社員5人、パート社員15人が介護職として働いている。
ちょっと変わった事業者名には、同社の理念が反映されている。「いる」は“共にいる”、「てる」は“いまを照らす”、「とわ」は“永遠に未来へ続く”。特に「いる」には、介護する側・される側の関係ではなく、一緒にいることができる存在でありたい……という願いが込められている。
定期巡回事業所「カイゴいるてと」は、地域の訪問看護ステーションと連携してサービス提供する「連携型」で、利用者の平均要介護度は3程度。スタッフのほとんどが喀痰吸引等研修を修了した介護福祉士。医療ニーズの高い利用者を看取りまで支援できる体制をとっている。
代表の前川さんは、訪問介護や老健、有料老人ホームなどの介護職として14年働いた経験を持つ。その後、フリーランスとして介護現場の業務や、コンサルティングなどを手掛けていた。そんな折、ある定期巡回事業所の見学をきっかけにこのサービスに魅了され、起業に向けた準備を開始。2023年4月に「カイゴいるてと」をスタートした。
定期巡回は、特に退院時支援と相性がいいと前川さん。病院では生気を失っていた利用者が、自宅へ帰った途端に元気になる事例は山のようにあると話す。
80代の男性Aさん。病院ではがん末期で寝たきり、吸引も必要な状態で余命1カ月と診断された。“最後は自宅で過ごしたい”とわが家に戻った翌日、前川さんが訪問すると、何とAさんは自力で、バリアフリーではない自宅のお風呂に入っていたのだ。
「本当にビックリしました。そんな利用者さんの自由な暮らしを24時間支える定期巡回は、介護職にとっても楽しい業務形態だと思っています」(前川さん)
最大の魅力は「柔軟性の高さ」だ。訪問介護では、ケアプラン上で提供時間と内容が決まっているが、定期巡回は介護職自身がその人のその日の状態を見て訪問のタイミングを調整したり、訪問回数を増やしたりすることができる。
例えば、要介護3で、糖尿病があり、ひとり暮らしの80代の女性Bさんは、朝起きるのが苦手だ。いるてとの介護職が訪問して声をかけても簡単には起きない。そこで、無理やり起こすことはせず、まず他の利用者宅を回る。その後でBさん宅へ電話をして起きていれば再度訪問。ご自身によるインスリン注射の接種などを見守る。低血糖症状が起こったときはコールを受けて、随時訪問を行っている。
こうした「柔軟性」は、介護職が本来やりたかった介護の実現につながっている。介護福祉士として事業所開設時から定期巡回や訪問介護に従事する菊池結希さんは、以前は介護施設の職員だった。決められた食事や入浴の時間に、寝ている入所者を無理に起こすのが自身にとってもストレスだったと振り返る。
「“この人、明日お通じ出るな”“そろそろ眠りが浅くなる時間だな”と本人の状態を予測した上で訪問して、本当にそうなると気持ちいいんですよ」と笑顔を見せる。
定期巡回の計画作成責任者の安部さおりさんは、訪問介護の加算にまつわる制約を指摘する。訪問介護の夜間や早朝の提供には加算があるため、利用者に負担が発生しないよう、あえて加算発生前の時間帯に提供に入ることがある。その点、定期巡回は包括報酬なので負担増を心配せず、「必要に応じて訪問できるやりやすさがあります」と話す。
一方で、特に夜間や緊急に対応できる人材の確保が難しい面もあるのでは……と尋ねると、「ありがたいことに“自宅にいるのだからその人のタイミングに合わせたケアをしたい”という考えの介護職が集まってくれて、定着率も高いです」(前川さん)という答えが返ってきた。フルタイム勤務の職員の直行直帰を認めたり、子ども連れでの打ち合わせもOKと、働きやすさに配慮していることも人材が充足している背景にあるようだ。「もっと成長して良い事業所になって、定期巡回は楽しく仕事ができて、人も集まるサービスなんだということを広めたい」と前川さんは目を輝かせる。
定期巡回はこれからが出番かもしれない。
いるてと前川代表(前列中央)と、介護職の皆さん

自宅での看取り時に利用者が好きな歌を歌う前川さん(左)