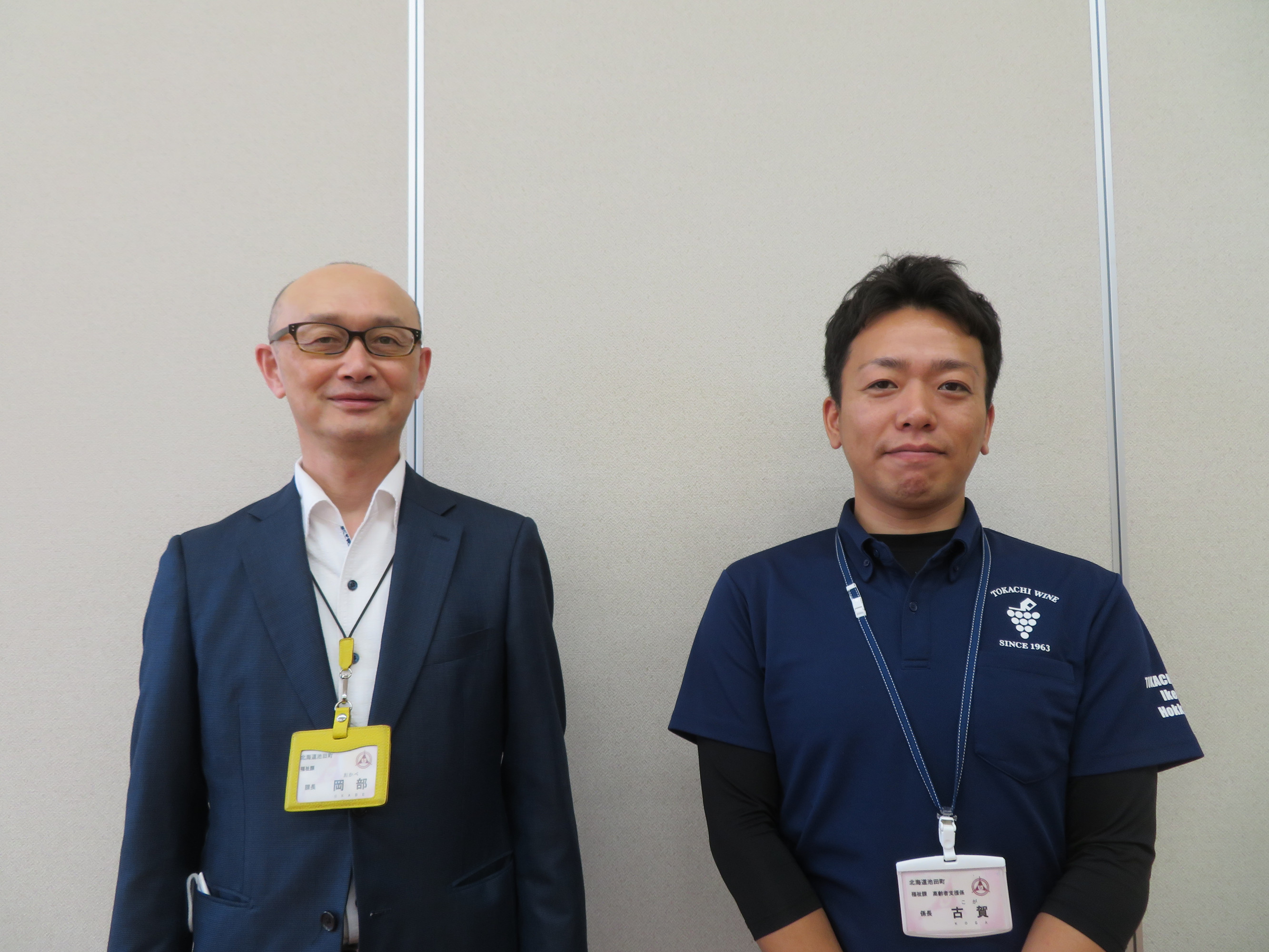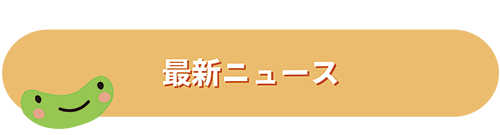- 2025/10/07
- バックナンバー
- 最新ニュース
北海道池田町では半世紀以上前に、町役場の組織に「いきがい課」という部署を設置して以来、高齢者のいきがい支援事業を続けている。事業の中心となっているのは町営の陶芸通所施設「池田町いきがいセンター」。通所者が制作した陶器作品は「いきがい焼き」と呼ばれ、町の特産品として多くの観光客に愛されている。作ったものを誰かに買ってもらえる喜びが高齢者の意欲を引き出しているという。
帯広市から電車で約30分の距離にある山間の町、池田町。池田駅から車で5分、大きな橋を渡った先にたたずむのがいきがいセンターだ。取材時点で18人の町民が通所登録しており、平均年齢は74歳。春~秋季は週4日で冬季は週2回、車や徒歩で通い、午前9時から午後3時まで陶芸作業を行う。最高齢で90歳の人は28年も継続して通所しているという。
作業場に併設されている販売コーナーにはコーヒーカップや皿、小鉢、箸置き、花瓶、フクロウや猫の置物など、様々な作品が並んでいる。その傍らで作業をする人々は手でろくろを回し、粘土を器の形に変えていく。陶器の着色も一つひとつ丁寧に行っていることから、同じものは一つとしてなく、全てが一点物だ。
「手ろくろの活用は、手先を鍛えることで認知症の予防につながっています。それだけでなく、形や色、模様などの絶妙な違いは個性となり、人を惹きつける魅力になっていると思います」
いきがい焼きが愛される理由について、陶芸指導員の藤田秀行さんはそう話す。近辺の観光施設やホテル、町内イベントなどでも販売されている作品の数々は人気が高く、売れ残りはほとんどないという。
作品は500~1千円程度のリーズナブルな価格で販売されているものが多く、売り上げの半分は制作者本人の収入となるが、月数千円から多くても数万円だという。通所者にやりがいを尋ねると、「自分で作ったものを誰かに買ってもらえることが嬉しい」と多くの人が誇らしげな表情を見せた。
手先を鍛えたことで家事が素早くなった人や、センター内外でコミュニケーションが活発になったという人もいる。飲食店に行った際は、どんな食器が使われているのか着目するなど、暮らしの中に新たな視点が生まれたという声も挙がった。「通所者のご家族からは会話が弾むきっかけになったという声が寄せられています。ご家族からのアドバイスで作品の幅が広がった方もいますね」と藤田さんはほほ笑む。
通所者は最初に、粘土の形作りなどの基礎を約2カ月に渡ってじっくりと学ぶ。その後は他の通所者と共に好きなものを自由に作り、作品の販売を目指す。指導のモットーは「必要以上に口出しせず、一人ひとりの創作意欲を尊重することです」と話す藤田さんが指導員を始めたのは33年前。20代の頃に趣味で陶芸教室に通っていたことから当時の町の福祉課長に入職を勧められたという。
「土の採取から始まり、粘土づくりや着色に使用する釉薬づくり、通所者が作った作品を焼く作業まで。制作指導にとどまらず、陶器が出来上がるまでのすべての工程に携わっています」
作品の販売や施設の修繕など、事業運営の多くを藤田さんを含む2人の職員で行っているというので驚いた。
「高齢者の方々が喜んでくれるなら今後も事業継続に努めたいと思います」
藤田さん(後方左)と通所者の皆さん。若々しくキラキラとした笑顔が印象的だ。
温かみのある色合いの作品
町長の事業発案から50年
いきがいセンターが開設されたのは1972年。池田町福祉課の岡部友博課長と古賀隼人高齢者支援係長によると、事業は当時の町長である丸谷金保さんによる発案から始まったという。
57年から約20年間、ブドウ栽培と町営ワイン製造などの多彩なアイデアで町づくりを進めた丸谷町長。町民の間で語り継がれている人物だという。今でこそ高齢者のいきがい支援は国を挙げて推進されているが、60~70年代は高度経済成長期の真っただ中。多くの人が経済的豊かさを追い求めていた時代で、高齢者の趣味や余暇活動を支える取り組みは珍しかった。そんな中、なぜこの事業が生まれたのだろうか。
「丸谷町長が当時の高齢化対策の先進国だったフランスの地方都市で養老院を運営する教会を視察したところ、高齢の方々がブドウ作りやワイン製造などの軽作業をしていたそうです」(岡部さん)
その頃、池田町の高齢者は既に家業を子供たちに引き継いでしまっている人が多かったという。丸谷町長の著書には、目を輝かせながら活発に働くフランスの人々の姿を見て「生活の保障だけでなく、お年寄りのいきがいをどこに見つけ出せるか」という考えに至ったことがきっかけだったと記されている。
その後、町内で焼き物に適した粘土が見つかった。これがいきがい支援に結び付けられ、事業開始の原点となった。
年間の運営費は約1200万円。対して、通所者が支払う参加費は春~秋季は月1千円、冬季は月500円と安価だ。古賀さんは「町の規模に対して運営費の負担は決して少なくないが、通所希望者は毎年途切れることがない」と話す。
「通所されている方々の介護給付費や医療費の負担がその分軽減されていると考えれば、費用対効果のバランスはとれていると感じています」
岡部課長(左)と古賀係長