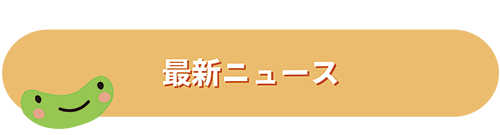- 2025/11/25
- バックナンバー
- 最新ニュース
超強化型の在宅復帰機能を発揮
東京都足立区の超強化型の老健施設「イルアカーサ」を運営する社会医療法人慈生会(足立区、伊藤雅史理事長)は、急性期病院から回復期病院、介護施設、在宅サービスなどの医療機関・介護事業所を総合的に運営し、急性期から生活期に至るまでの各ステージに合わせたリハビリを提供している。その法人内の各機関がICTやAI、センサーを活用して切れ目なく情報共有・連携し、患者・利用者の状態を予測・把握しながら在宅復帰につなげている。
「イルアカーサ」は、2014年に開設した入所定員100人、通所リハや訪問リハも提供する老健施設。施設名はスペイン語で「家に帰ろう」という意味で、その名の通り、病院などから入所した高齢者が早期に自宅へ帰れるようリハビリや医療・介護を提供する「超強化型老健」だ。月平均10人ずつの入退所がある。
社会医療法人慈生会は、急性期の等潤病院を母体に、回復期リハ病棟、地域包括ケア病棟、老健施設、訪問・通所リハ、地域包括支援センターなど医療・介護サービス事業を運営。提唱する「トータルヘルスケア」の基盤として、医療機関の電子カルテシステム、介護施設・事業所の介護カルテシステムの患者・利用者情報を一つのIDで管理する独自のネットワークを構築している。
コロナ禍では、ICTを活用した情報共有がより活発になった。家族の面会制限だけでなく、入所者の居宅訪問、法人内の事業所同士も対面でのやりとりができなくなったため、介護職やリハビリ職を含む全職種にiPhoneを支給。入所者のリハビリや生活の様子を動画や写真で撮影し、法人内事業所や、家族、外部のケアマネに説得力を持って伝えることで自宅へ帰る際のスムーズなサービス調整ができたという。
通所リハビリでは2024年から、歩いている姿をスマホで撮影すると歩行を点数化し、未来の状態予測、改善のための運動などを1分程度で示す筑波大学監修の歩行解析AIアプリ「リハケア」を導入。「リハビリテーションマネジメント加算」の算定要件である「定期的なリハビリ会議」に参加する専門職が評価結果を共有し、リハビリ計画を検討、見直しに役立てているほか、本人や家族にも情報をフィードバックし、リハビリの意欲向上につなげている。
「入所してくる前にその人の動作を確認し、リスクも共有できるのが利点です。状態が“見える化”されるので若手のセラピストの学習ツールとしても活用しています」(リハビリ主任の篠﨑祐貴さん)
2年前からはインカムも導入。通所リハビリを行うリハビリ室は横に長く、お風呂がフロアの片側の端にあるため、リハビリや入浴などで評価したことを職員間でタイムリーに情報共有して柔軟に動くのに苦労していた。インカムの導入によって職員の移動のロスがなくなり、負担軽減と円滑な情報共有が実現できたという。
入所フロアでは、パラマウントベッドのシート型センサー「眠りSCAN」を、20年に100床全床に導入。睡眠時の心拍数や呼吸数などのデータに基づき介護職が個別ケアや看取りを提供しているが、リハビリ職もデータを見て利用者のその日の状態にあったリハプログラムを立案している。
このようにICTやAI、電子カルテシステムなどで業務効率化を図り、平均入所8カ月で利用者を在宅へ帰しているイルアカーサだが、効率化一辺倒ではない。アクティビティと一体的に提供するリハビリには手づくりの温かみがある。
例えば、「ぶどう狩り」。ぶどうの実や房を利用者が紙で作り、それをネットを張ってぶら下げ、車いすに座った状態から手を伸ばして収穫する。ステンドグラス風の塗り絵など多様なアクティビティを施設のPTやOTが企画から担っている。
「楽しんでリハビリをやってもらうために一生懸命考えています。介護分野はその人の生活に丸ごと関わるので、“PTだから歩行訓練や可動域訓練だけ” ではないですね」とリハビリ主任で理学療法士の福田匠さんは笑う。
屋上農園では園芸活動も。収穫期には、リハビリ職が利用者の体を支えた上で、さつまいもなどを掘ってもらう。「リハビリ室で行うリーチ訓練以上に、体や手を前に伸ばすことができるんです。 “やりたい”という利用者の意欲が、生きた動作を引き出しますね」
連携と共有、効率化と生活感が適度なバランスで共存するリハビリ現場だ。
イルアカーサのリハビリ職(前列3名)と介護職、事務の皆さん
「リハケア」の結果は利用者にも共有

屋上農園で利用者も腕を伸ばして芋掘り