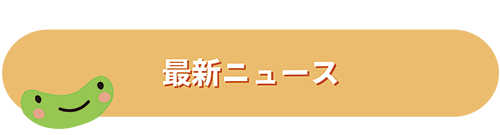- 2025/10/10
- バックナンバー
- 最新ニュース
一家共倒れの危機でも父親の入所に母親が反対
息子が幼稚園に通い始めたころ、母親が転倒して左手を骨折します。それをきっかけに、母親の心身の衰弱が一気に進んでいきました。自らががんになっても、免疫力に関わる血液中の白血球の働きが「笑うと増える!」と、東北生まれなのに大阪のオバちゃんのノリで病室のみんなを笑わせる〝笑わせ隊”を名乗るなど、どんなときでも前向きだった母親。そんな母親から笑顔が消え、「もう頑張れない」なとど弱音を吐くようになり、どんどん痩せていきました。父親の通院に付き添った母親を見た、父親の主治医があまりに衰弱した姿に驚き、父親の施設入所を促すほどです。
私は父親の介護とともに母親のサポートの量もどんどん増えていきました。加えて、発達障害を抱えた息子の育児と療育もあります。「このままでは私が倒れてしまう」と、私からも母親に父親の施設入所を提案すると、まさかの母親は大反対。20年近く在宅で父親の介護をしてきたという意地と、世間体を気にしているようなのです。その気持ちもわかりますが、以前の私は一人で抱え込み過ぎて心身のバランスを崩してしまいました。今度は息子を育てる母親として、同じ過ちを繰り返すわけにはいきません。たとえ、話し合ったことを忘れてしまっても、父親に現状を話して、施設入所を納得してもらいました。反対する母親に対して、人に助けを求める重要さをこれまでの介護で学んだ私は、父親のケアマネジャーや、母親のかかりつけ医、ご近所のおばちゃんなどにも協力を仰ぎました。家族より他人の話のほうが聞く(効く)ようで、どうにか母親も納得してくれたのです。
入所の覚悟が決まったら、父親に合いそうな施設を見つけるための見学です。同行した母親が「あなたが入所されるのですか?」と施設のスタッフに間違われながらも、最終的には10施設くらいを見学。それぞれに特色があり、実際に足を運ばないとわからないことが多くありました。そして、「ここならばお父さんが安心して生活できそう」という施設に申し込みをしたのです。70代の父親にはまだまだお金が必要だとして、比較的料金の安い公的な特別養護老人ホーム(特養)に的を絞りました。一方で、特養は待機者が多く、すぐの入所が難しいとされています。それは入所希望者の抱えている状況を加点式で見ていき、点数の高い人から入所が決まるからです。書類に現状を枠からはみ出すほど書きましたが、順番は100番台。ケアマネジャーの提案で、母親の介護申請を再びすると要介護2という判定に。思っていたよりも状況が悪化している母親に落胆しつつも、改めて現状を書類に書き加えて、施設の関係部署へ再提出。その後も施設に直談判(泣き落とし!?)に行くなどで、順番は10番台に。申し込みをして約10カ月後、希望していた特養に父親は入所することができました。こうして、次は母親のための在宅介護体制を整えていくことになったのです。(続く)
(プロフィール)
おかざき・あんり 若年性認知症の父親の介護と卵巣がんになった母親の看病を20代から担う。その後、子育てと介護が同時進行のダブルケアラーに。著書に自らの経験をつづった『笑う介護。』(成美堂出版)など。
オフィシャルサイト https://anriokazaki.net/
【前回】
https://silver-news.com/blog/detail/2922
【次回】
https://silver-news.com/news/detail/3370