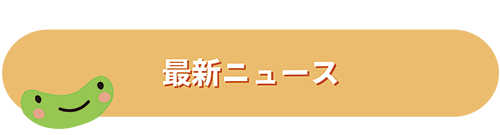- 2025/11/07
- バックナンバー
- 最新ニュース
施設に入所しても家族の介護は続く
母が亡くなったのは、コロナ禍で増え続ける感染者数を、連日、ニュースで読み上げている頃でした。父に母が亡くなったことを知らせると「俺が喪主をする」と、急に凛々しい顔になり夫としての努めを果たそうとしています。ただ、世界中で「ステイホーム」が叫ばれ、免疫力の低い高齢者が暮らす施設は感染症対策に細心の注意を払い、外出どころか面会も禁止されていました。父が母の葬儀に参加することを諦めていると、施設のスタッフが「奥さんと最後のお別れをさせてあげたいので、できる限り対応します!」と外出を特別に許可してくれたのです。その心遣いには、感謝しかありません。
斎場で母の亡骸と対面した父は、冷たくなった母の頬を撫でて静かに涙を流していました。きっと父なりの母とのお別れをしていたのでしょう。一方で、私も母のことを悼みながらも父の車椅子を押し、斎場の多目的トイレで父のオムツ交換。父の介護にバタバタと走り回る娘を上から見ていた母は「こんなときまで、いつも通りだね」と笑っていたに違いありません。
その後、コロナにより面会が思うようにできない中でも、施設で穏やかに暮らしていた父でしたが、昨年の夏に体調を崩します。「丸1日以上ご飯を食べないので、病院に連れていった方がいい」と施設から私に連絡が入りました。施設に入所しても、医療保険に切り替わる病院では、介護保険が使えないため基本的には病気になると家族が対応するのです。父は胆石による胆管炎を起こしていました。処置室が空き次第、胆管炎の処置をすることになり、私は何時に帰宅できるかわからない状態。急な父の病院対応で発達障害の息子が何も知らないまま母の帰りを待ちつづけてパニックにならないかと心配になりました。夫に連絡するも仕事中のため繋がりません。家に電話をすると息子が出たので現状を説明すると「それは大変だ」と、1人で留守番を頑張ると言ってくれました。意外なところで息子の成長を感じた出来事でした。
その後も胆管炎を繰り返した父は、胆のう摘出手術を受けることになりました。そのための数々の承諾書へのサインなど、入院中のあれこれはすべて家族が対応しなければなりません。また退院後も施設からの通院が必要になるため、病院に行くための車の手配とその車には家族の同乗が求められ、病院では常に父に付き添い、薬の受け取り、病院と施設が情報共有するためのやり取りなど、通院日は父の対応で1日が潰れてしまいます。さらに仕事の調整や息子の対応、家事も同時進行でどうにかしなくてはなりません。急に私の生活は多忙になりました。要介護の家族が施設に入所すれば、家族の介護の負担はかなり軽減されます。それでも、まったく介護をしなくなるということはありません。このときの父のように医療的な事態が発生したり、家族にしか対応できないような事態が起きたときは、施設に入所していても、また新たなかたちで家族の介護は続いていくのです。(続く)
(プロフィール)
おかざき・あんり 若年性認知症の父親の介護と卵巣がんになった母親の看病を20代から担う。その後、子育てと介護が同時進行のダブルケアラーに。著書に自らの経験をつづった『笑う介護。』(成美堂出版)など。
オフィシャルサイト https://anriokazaki.net/
【前回】
https://silver-news.com/blog/detail/2958
【次回】
https://silver-news.com/blog/detail/3006